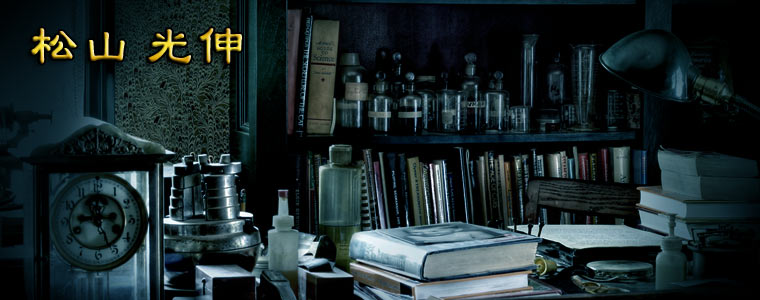
第2回 評判になったタカセの日本手品
その後のタカセは引っ張りだこになります。
確認できただけでも、翌2月はランカシャー州のダーウィン(Darwen)にあるロイヤル劇場(The Royal)、その1週間後には同じランカシャーのアクリントン(Accrington)にあるヒッポドローム劇場(Hippodrome)、3月には南隣のチェシャー州のランコルン(Runcorn)にあるパレス劇場(The Palace)、4月はペイズリー(Paisley)のヒッポドローム劇場、などと休む間もなく動き回り、5月に再びロンドンに戻ってセント・ジョージ・ホールに出演するといった忙しい日々を送ります。
そこにはすでに一人立ちしたマジシャンの姿がありました。
実際、彼がどのようなマジックをどんな手順で演じたのかに興味をそそられますが、
幸いにも詳細な演技内容がThe Magical Worldに寄せられていました。
それは1913年7月9日号に掲載されています。
寄稿者は不明ですが、ロンドンのイズリントン・エンパイヤ劇場(Islington Empire)での7月3日演技の模様が伝えられています。
 |
絵のような衣装を身にまとった飾り気のない小さな日本人が、ユニフォーム姿の二人の助手に見張られたキャビネットが置かれたステージの正面に進み出ます。
あとは長めのロープといくつかの小物を載せた二つの小ぎれいなテーブルがあるのみです。タカセはまず白い素材でできた細長い一片を巧妙に捩じって畳んでいくとそれが彼の衣装の一部になってしまうという現象から芸を始めます。
小さな紙片が燃やされ、その灰を投げると薄い紙リボン状になって観客席の上に広がります。
これを素早く手元に引き寄せてまるめ、水の入ったガラスコップに浸し、その濡れた塊を扇子の要の部分を使って取り出し左手に受け取ると、細かな紙吹雪となって舞い広がります。
次に一人の助手が前に進み出て演者の両手首を縛ります。
一繋がりの白い木綿のロープを輪になった両腕の中を通して彼を繋ぎ止めるのですが、ロープは縛られた両手首からすり抜けたかのようにタカセは即座に脱出してしまいます。
次に、蓋のない四方に側面があるだけの箱と取り外し可能な底板を示します。
最初は空っぽです。一枚のシルクのハンカチがその中に投げ入れらたかと思いきやすぐに消えてなくなります。
そして再び出現したかと思いきや、次々と他のハンカチも現れます。
その都度箱はバラバラにして何も仕掛けがないことが示されます。
最後に長いリボンが中から出てきて、それらを一緒にまとめてキャンドルの火にかざすと突然火花が飛び散ってそこから日本の旗が出現しそれを舞台上に広げます。
残っているリボンから更に旗竿に結ばれた大きなユニオンジャック(イギリスの国旗)を出現させ演者はその陰に引き下がります。
わずか1、2秒後、彼はスマートな西洋式の正装に身を包んでステージに姿を現します。
彼はフットライトのところまで進み出て、客席から二人の紳士をお手伝い役として招きます。
演者は特別製のコード(訳者注:複数形なので2本とわかります)を使って両親指をきつく縛らせます。
そしてこの状態でお手伝いの客が投げた二本の輪を指が結ばれているにもかかわらず腕に通して受け止めます。
これらの輪は客の手によって外されますが両親指は結ばれたままです。
タカセは結ばれたままの両手を客の両腕に繋ぎ、それを再度外して見せますが、そこには何も怪しい動きはありません。
間違いなく天一のサムタイの最高のバージョンで、これを目にすることが出来たことは大きな喜びでした。
キャビネットが舞台前方に移されます。
演者はコートを脱いで 二本のロープを取り上げます。
キャビネットには仕掛けのないことが示され、椅子が一脚キャビネットの中に入れられます。
二本のロープが演者の首に巻かれて縛られ、さらにもう一度首元で結ばれます。
次いでロープは演者のベストの両サイドの腕の辺りを抜けて袖口に出します。
そこで演者はキャビネットに入り両サイドは閉じられます。
ロープは椅子の下の支柱をくぐり、さらにキャビネットの両サイドに開けられた穴を通過して、舞台に上がってくれた二人の紳士の袖口に通します。
目隠しをするためカーテンが演者の前に引かれます。ピストルの音が鳴って彼が脱出したことが告げられます。
ロープが助手の手でたぐり寄せられ数々のからんだ障害物から抜け出ると、
キャビネットが勢いよく開いてタカセが自由の身になって出てきたと思いきや、オペラハットに裾の長いマントに身を包んだ姿で現れます。
並外れた素晴らしい演技でした。
いまでも十分通用する素晴らしい演技に観客が大いに楽しんだ様子が生き生きと描かれています。特に日本手品だけでなく、スピリット・キャビネットにヒントを得たロープからの脱出芸や、いまでいうところのコスチューム・チェンジなどを組み合わせたビジュアルでメリハリのあるその演出からは、経験にもとづく工夫が随所に取り込まれていることが見てとれます。ただ、それまで天一一座や天二一座で演じていた水芸はもはやレパートリーにはありませんでした。道具を新たに制作するのが難しかったというよりも、一人では演じたくとも出来なかったのです。ちなみに先の公演プログラムに載っているタカセの姿は「両手首を縛って腕が輪になったところに助手がロープを掛けて抜けられなくした状態から脱出する」という芸を演じているところです。これは1764年の『放下筌』の中に出てくる「綱抜き」でトポロジーの原理によるもののため現在ではパズルブックや子供向けの入門書に見られる程度になっていますが、それをプロの舞台芸に仕立てたところに彼の非凡さが感じ取れます。
結婚と子供の誕生
マジックの殿堂セント・ジョージ・ホールのステージを踏んで丁度一年になる1913年の暮れ、経済的に安定したタカセは家庭を持つことにしました。お相手は4歳年下のファニー・パー(Fanny Parr)。その届出書を見るといろいろなことが分かってきます。届け出時点の住所を見ると、タカセはランカシャーのブラックプール市(Blackpool)で、新婦はランカシャーのアクリントン(Accrington)でした。この二か所は地理的に比較的近いとはいえ行き来できるような距離ではなく、どこで知り会ったのか少し気になるところです。タカセの住所として記されていたところは仕事で一時的に宿泊していたところと考えられますが、届け出を行ったハズリングデン(Haslingden)という町は、ファニーが住んでいたアクリントンに近く、当時はアクリントンの住人の戸籍登録業務も行っていたためここに届け出たという事情が分かりました。
一方、二人の出会いの場もすぐにわかりました。前述したように、タカセは彼女が住むアクリントンのヒッポドローム劇場でその年の2月に公演をしていたのです。彼女の職業欄にあるLaundry Handというのはランドリーの仕事についていたことを意味します。いずれにせよアクリントンでの興行中にホテルから時々このランドリーに洗濯物を持ち込んだ時に知り合いになったものと推測されます(もしかしたらホテル内にこのランドリーがあったのかも知れません)。雑談するうちにファニーは彼が近くの劇場に出ていることを知ることとなり、親しみを感じて実際に観に行ったり、タカセの方からチケットを貰ったりして急速に親しくなったのでしょう。ファニーの両親はタカセが家をあける機会が多いマジシャンである点を気にしたかもしれませんが、いずれにせよ、その年の末に晴れて結婚することになりました。

|
(座席数1600、立見含め2000名収容可能。出典:The Era, 1909/1/2)
この結婚届のフォームの右側にはそれぞれの父親の名前と職業を記すようになっていて、それによってタカセの父親がガラス吹き職人(Glass Blower)であったことが分かったのですが、ファニーの方にはそれらが記されてなかったため(横線が引かれている)新婦側の家庭の背景等について詳しいことはわかりません。
結婚後の活動
各地を巡り歩く機会が多いマジシャンの場合、結婚後は夫人がアシスタントを務めるケースはよくあることです。ただ、タカセの場合、結婚した時点ですでにファニー夫人は5ヶ月の子を身籠っていました。各地を頻繁に移動する興行稼業としては一緒に連れまわすわけにはいきませんでした。そして翌1914年5月末に女の子が生まれました。出生届は夫人が行い、生まれた女の子にはリリアン・ハナ(Lilian Hana Takase)の名が付けられました。父親の職業欄はイリュージョニストと記され、届け出時の夫人の住まいは結婚前に住んでいたアクリントンの住所と同じ番地が書かれていました。この記録から、ファニーは結婚後出産を控えて実家に戻り、そのまましばらく両親のもとで母子ともに過ごしていたことが分かりました。
母子を預かってもらったタカセは、5月初めにはロンドンのヒッポドローム劇場で、
下旬には南部の港町サウサンプトンで活動し、
6月はダブリン(当時はイギリスの一部)まで足を延ばします。
そして8月には再度セント・ジョージ・ホールに戻って出演するなど従来通りのペースを崩すことなく各地を回っています。
きっと興行先が替わるタイミングをとらえながらファニーの実家を訪れるという生活を繰り返していたのではないでしょうか。
 |
ここにある“Walking Through a Wall”(ブロック壁の通り抜け)は
P. T. セルビットが2か月前に初演した有名なマジックです。
≪ 第1回 第3回 ≫
著作権は各記事の筆者または(株)東京マジックに属します。
Photo: study by CodyR