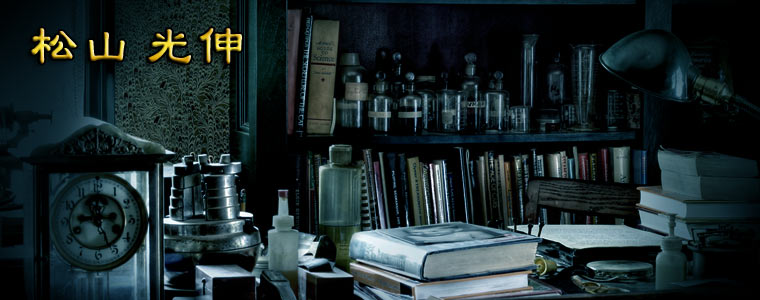
国際芸人の先駆者、ジンタローの生涯
第2回
幕末の渡航芸人の確認
とりあえず確認した書籍として、「1885年ロンドン日本人村(倉田喜弘著)」、「大世紀末サーカス(安岡章太郎著)」、「ニッポン・サーカス物語:海を越えた軽業・曲芸師たち(三好一著)」、「海外公演事始(倉田喜弘著)」、「海を渡った幕末の曲芸団:高野広八の米欧漫遊記(宮永孝著)」等に目を通したが、いずれもGintaroの名前は出てこないばかりか、これらの実録本に出てくる人物は、まさに開国にあわせて渡航したチョン髷・帯刀の出で立ちの人物が多いことがわかった(モノ珍しさも評判が高かった要因とされている)。加えて、欧米人の興行者のアレンジによって公演スケジュールが設定され、引率されながら数年で帰国したケースが中心で、現地で根を張った芸人の活躍の記録はほとんどないことがわかった(注1)。
また、芸団協を通じて太神楽曲芸協会会長の鏡味仙三郎師匠(曾祖父の鏡味仙太郎が明治に渡航し評判をとっている)や伝統芸能に詳しい土居郁雄氏に問合せをするとともに、日本芸術文化振興会を通じて日本芸能史研究の第一人者である倉田喜弘氏等にもご意見を求めた結果、いずれもGintaroの名ははじめて聞く名前とされた。また、彼が記述しているいくつかの曲芸の起源についても、ジャグリング研究家の西川正樹氏が噂を耳にしたことがあるだけで、他は誰も聞いたことがないということがわかった。ここに及んで、更に調査を進めて紹介することがムダではないことを確信するとともに、むしろ紹介しなければいけないという義務感が湧いてきた。
一方、この過程でGintaroにかかわる非常に貴重な情報が一つ得られた。それは、「現地の芸能ニュース紙であるAlly Sloper’s Half Holidayの1891年の12月12日号の中でGintaroの演技が報じられていて、その中に英国の演芸場ならどこにも出演している人物で、水中曲芸などを演じたように書かれている」という情報がもたらされたのである。
とはいえ、Gintaroはこの時期まだ少年のため、どこにでも出演していたという実績があるとは考えにくく、また、単なる曲芸ではない水中曲芸を行なっていたとなると、それがどういうものだったのか実際の記事などを確認しないと納得できるもの話でもなかった。信憑性がハッキリしないまま、それに頼ったGintaro伝をまとめることは意味がないからであり、以後、細かな元資料を掘り起こしながらGintaroの足跡を追うことになった(注2)。
マスケリンとデバントのショーへの参加
 |
マスケリンのショーが移った直後のポスター
この時点で、既にわかっていたことを記しておこう。それは主として「セント・ジョージ・ホール」の本の中に記されていたものである。
- J.N.マスケリン(マスケリン一族の中でも最も有名な英国奇術界の大立者)は、ジンタローのことを評して、99年間の契約をしたい人物ということをいつも口にしていたこと。これは英国が香港を99年間租借する契約をしたことになぞらえて語ったもの。
- 1905年にセント・ジョージ・ホールに移った直後のマスケリンの新しい出し物は評判が悪く見直しを余儀なくされたが、内容の大変更に伴ってジンタローが起用されることになった(これ以降ショーは大きく持ち直す)。なお、この再起公演(4月22日が初演)の最初のプログラムには、デバントとジンタローの2枚看板のポスターが描かれている(写真5)。
- セント・ジョージ・ホールには、その後頻繁に出演を繰り返すことになるが、この劇場で演技した記録が確認できるのは1930年迄であった。
- 1906年に行なわれた、ザ・マジック・サークル主催の英国ベストマジックショー(The Magic Circle First Magic Seance)には、並み居る当代のトップマジシャンに並んで出演をしている(写真6)。例えば出演者の中に見えるネイト・ライプシック(Nate Leipsic)とはプロフェッサーの敬称で世界から慕われたダイ・バーノン氏が最も敬愛したボードビルの名手ライプジックであり(Leipzig:独語読みではライプツィッヒ)、Joad Hetebとは後に「美女の胴体切断」を発案したことで有名なP. T. セルビットのことである。
- マスケリンとデバントの一座からの海外派遣ショーとして、1907年にはデビッド・デバントと一緒にウィーンに、1908年には、オーウェン・クラークと一緒にオーストラリアとニュージーランドに行き、興行を成功させている。
- マスケリンとデバントは彼らのショーに貢献した人物として過去二人だけに謝意を表す金メダルを贈っているが、ジンタローはその一人だった。このことから彼らにとってジンタローが如何に重要な役割を担っていたが分かった。
 |
ベスト・マジック・ショーのプログラム
特に驚いたのは、途中地方遠征等で留守をすることはあるにせよ、セント・ジョージ・ホールだけでも25年にわたって出演をしていることである。ひるがえって現在のニューヨークのブロードウェーやラスベガスを見ると、何年にもわたって一流劇場でマジックショーを継続できている例は数えるほどでしかなく、ましてや日本人がそういう場で長く活躍している例など現在でもほとんどなく、まさに偉業といってもいいことなのである。そして、この後、ポツポツといろいろな新事実が判ってきた。
ジンタローの演技評
まず、ストランド・マガジンの記事の発行時期であるが、これは1914年の12月号だったことが判明した。一方、1906年に行なわれたThe Magic Circle First Magic Seanceについては、エリス・スタニオン氏(Ellis Stanyon)編著の月刊MAGICに細かな演技レポートが書かれていたことが分かった。この月刊誌はマジックのみならずボードビル芸を含めた芸能評論紙の性格を持つ雑誌で、数年前に合本の形で復刻された歴史的に価値のある資料であるが、その1906年5月号に掲載されているのである。
記事を書いたのはスタニオン氏自身で、出演者それぞれに対して演技内容について記述しているが、そのコメントを見ると、他の一流マジシャンに対するものと比べ、ジンタローに対しては圧倒的に多くのスペースを割いていることが注目された(数行とか、半ページの記事が多い中で、ジンタローについてはフルに2ページ使って紹介している)。
 |
ジンタローの演技の記事
これを読むと、ジンタローの芸がどういうものであったかが判ってくるが、英国人芸能評論家の目を通して紹介されていたのは、傘を使った小物を回転させる芸、独楽の芸(両手に持った2枚の羽子板状の板も使った演技)、ブロックを使ったバランス芸、水がめを両端にぶら下げたロープの芸等で、スタニオン氏が過去に見た日本人や中国人の曲芸と比較したコメントや、更にはスタニオン自身のアイデア等も記述しており、ジャグリング研究家にとっても興味ある記事となっていた(写真7)。
また、これとは別に、1907年の1月号でもスタニオン氏はジンタローの芸を取り上げており、そこには、曲独楽が糸を伝って駆け昇り、上方に吊り下げられた小箱に飛び込んだ瞬間、その反動で飾り箱の仕掛けが開いてデコレーション豊かなフィナーレとなる芸を興味深く観察するなど、分析的な記述が行なわれている。
太神楽曲芸に詳しい日本人がこれを見るとあまり驚くほどの内容には見えないかも知れないが、通常の太神楽芸の範疇を超えた芸域と、それを12才の時に渡航した少年が異国で演じ評判になっていたということは大変なことなのである。
注1: 唯一の例外は沢田豊である。ただ、彼の渡航はGintaroより25年遅い1902年で(当時16才)、横田一座の一員としてロシア経由で欧州に渡り、ドイツのサラザニ・サーカスの看板スターとしてその隆盛に大きな役割を果たした。彼は、ドイツ人を妻とし、子供を芸人に育てながら各国を巡り、ドイツのゲッティンゲンで生涯を閉じた。その人生は大島幹雄著「海を渡ったサーカス芸人, 1993, 平凡社」に再現されている。)
注2: ちなみにGintaroとは当初ギンタロー(銀太郎、或いは吟太郎)と考えていたが、最終的にはジンタローであることが分かった。
≪ 第1回 第3回 ≫
著作権は各記事の筆者または(株)東京マジックに属します。
Photo: study by CodyR